1. 登記とは
不動産の「登記」は、法務局にその権利関係を記録して第三者に対して主張できる状態(=対抗要件)にするための制度です。
契約で当事者間の権利が発生することと、登記で第三者に主張できることは別の話です。実務では「残代金の支払い・引渡しをもって権利移転」が当事者の合意で決まることが多く、そこで登記を速やかに入れるのが実務上の鉄則です。
車でいえば車検証に名前が載るようなもの――外から見て誰のものかが分かる公的な帳票、というイメージが近いです。
2. 司法書士の役割
決済(残代金の授受・鍵の引渡し)の場で司法書士が立ち会い、次の業務をワンセットで実行します。
- 売主・買主の本人確認(名義の真正性確認)
- 必要書類のチェック(権利証・印鑑証明・委任状等)
- 所有権移転登記の申請(登記原因を添付)
- 旧抵当権の抹消申請と、新抵当権設定の申請(融資がある場合)
要点は、司法書士が「合意どおりの権利移転を、対抗要件まで含めて確実に行う最後の責任者」であるということです。ここが手薄になると、対抗できないリスクが生じます。
3. 地面師事件
地面師事件とは、他人の土地の名義人になりすまして売却したように見せかける詐欺事件です。
偽造書類を駆使し、本物の所有者のふりをして契約を進め、多額の被害を生んだことで大きな社会問題となりました。
この事件はあまりの衝撃から、Netflixのドラマ『地面師たち』として映像化され、一般の方にも広く知られるようになりましたね。
ドラマでは、司法書士が本人確認や書類精査を通じて詐欺と闘う姿が描かれています。
まさに「登記を誰がどう扱うか」が勝負を分ける展開で、司法書士の役割と登記の重要性が分かりやすく伝わってきます。。
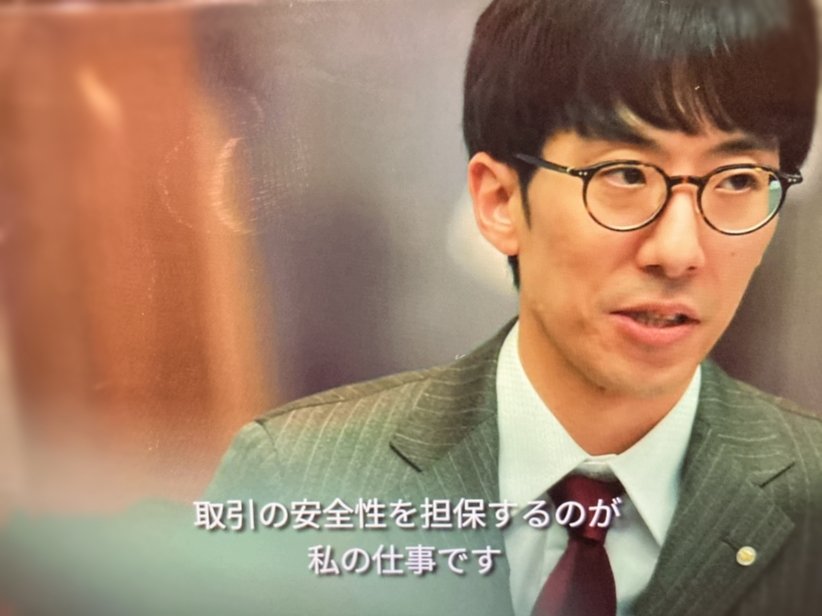
登記上の所有者と目の前の売主が同一人物か、この本人確認が肝でしたね。

こちらも元司法書士という設定でしたね。
4. 「自分で登記する」は悪いこと言わんからやめとけ
法律上は可能でも、実務では非常に危険で、特に銀行融資が絡む取引ではほぼ許容されません。以下、具体的に起こり得る問題を挙げます。
A. 銀行が融資を実行しない/融資条件を満たせない
多くの取引で銀行は「登記による抵当権設定が確実に行われること」を融資実行条件にします。買主が自分で登記するという状況は、銀行から見ると「担保が確保できない可能性」があるため、融資を止められるか、実行が遅れます。融資が止まれば決済そのものが崩れ、違約金や信用リスクが発生します。
B. 書類不備で申請が差戻される・却下される
登記申請は必要書類の形式や記載が厳格です。住民票の住所表記揺れ、印鑑証明の有効期限、委任状の記載漏れなどで申請が差戻されると、決済時に登記を完了できません。差戻しの対応で時間がかかると、先に述べた融資の問題や第三者の先登記リスクが顕在化します。
C. 先に第三者が登記を入れる(先登記のリスク)
登記は「先に登記をした者が優先される」ルールがあります。手続きを自分でやっている間に第三者(悪意ある者や売主が二重売却した場合の別買主など)が先に登記を入れれば、当事者間の契約があってもその第三者に対抗できない可能性があります。
D. 抵当権の抹消・設定ミス
中古物件では、売主の抵当権を抹消してから買主の抵当権を設定する、という連続手続きが必要です。これを誤ると旧抵当権が残留したままという状態になり、将来の売却や資金融資に支障を来します。
E. 決済スケジュール全体の崩壊と損害
登記ミスや遅延は、売主・買主・仲介・銀行の全員のスケジュールを止め、違約金や信用喪失、事務コスト増を招きます。節約した数万円が、時間・金銭・機会損失で大きく上回ることが普通に起こり得ます。
5. まとめ
- 不動産は「契約した=自分のもの」ではなく、登記をして初めて第三者に主張できる
- 決済の場では司法書士が立ち会い、本人確認や書類精査、移転登記や抵当権関連を一括処理する
- 地面師事件のように「登記名義を悪用した詐欺」が起きており、名義の真正性確認こそが重要
- 「自分で登記する」は、リスクが高いうえ、銀行が抵当権設定を許容せず実務上ほぼ不可能
- 節約の対象ではなく、安全に取引を終えるための必須コストとして司法書士に任せるべき
ご相談はこちらから
不動産の購入や売却に関するご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
では、またひみつ基地で!




コメント